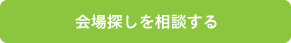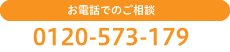暑気払いとは?意味・由来・時期・納涼会との違いをわかりやすく解説
2025/7/29
暑気払いとは、夏の暑さを乗り切るために行われてきた、日本の伝統的な風習です。
現代では、企業や団体での飲み会・食事会として広く知られていますが、本来の意味や開催時期をご存じですか?
この記事では、暑気払いの由来や納涼会との違い、開催時期の目安などをわかりやすく解説します。初めて企画する方も、開催の意味を知りたい方も、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
暑気払いの意味、本来の目的とは?
暑気払い(しょきばらい)とは、夏の暑さで疲れた体をいたわり、元気を取り戻すための行事です。古くは江戸時代にも、暑さをしのぐ風習として親しまれていました。語源となる「暑気」は、暑さによる体調不良やだるさなどを指し、これを「払う」ことで健康を保つという意味合いがあります。
現代では、企業や団体が暑気払いの名目で食事会や飲み会を開くことが多く、夏の労をねぎらい、チームの親睦を深める機会として活用されています。
暑気払いと納涼会との違いとは?
「暑気払い」と混同されやすい言葉に「納涼会(のうりょうかい)」がありますが、実はそれぞれ意味や使われ方に違いがあります。
| 暑気払い | 納涼会 | |
| 目的 | 暑さで疲れた体をいたわり、夏バテを防ぐことが本来の目的 | 暑い中でも涼を感じながら楽しむことが目的 気分転換や親睦を深める意味合いが強い |
| 開催時期 | 梅雨明けから土用の時期(7月上旬〜中旬)に行われることが多い 暑さ本番前の準備という意味合いがある |
より夏の盛りである7月下旬〜8月にかけて開催される傾向が強い |
企業や団体によって呼び方はさまざまですが、どちらも「夏の交流会」として親しまれている点は共通しています。言い換えが可能なケースもありますが、「季節感」や「由来」にこだわるなら、時期や趣旨に応じて呼び分けるとより丁寧です。
暑気払いの時期の目安と背景
暑気払いは、一般的に梅雨明けから土用の期間(7月初旬〜中旬)に行われることが多く、夏本番を迎える前に体調を整えるという意味合いがあります。暑さが厳しくなる前に開催することで、季節の変わり目に体調を崩しやすい時期を乗り切る準備をするという、日本らしい風習です。
近年では、企業やグループの都合に合わせて7月下旬〜8月初旬に開催されることも多く、厳密な時期の決まりはありません。
より詳しい開催時期の目安や、準備・スケジュールについては以下の記事もご覧ください
暑気払いで食べられてきたもの・飲まれてきたもの
暑気払いでは、昔から「体を冷やす」「元気をつける」ことを目的とした食べ物や飲み物が用いられてきました。
たとえば、江戸時代などでは、暑さを和らげるための甘酒や梅ジュース、冷たい麦茶などが親しまれていたと言われています。また、滋養をつけるためにうなぎや夏野菜を使った料理が振る舞われることもありました。
現代の暑気払いでは、ビールやハイボールなどの冷たいお酒が定番となり、冷菜・スタミナ料理・スパイス系メニューなど、「夏らしさ」や「見た目の涼しさ」を演出するメニューが好まれる傾向にあります。
会社の食事会や飲み会として開催されることも多く、いわゆる「夏の飲み会」=暑気払い、という形で定着しています。暑気払いの料理や飲み物に悩んでいる方は、以下の記事もぜひご覧ください。
暑気払いにおすすめの料理と飲み物は?夏らしさを感じるメニューや差し入れも紹介
暑気払いって必要?今どき開催する意味とは
近年では、職場の飲み会に対して「業務時間外に参加したくない」「気を遣うから疲れる」といった声も増えており、暑気払いの必要性を感じにくい方もいるかもしれません。しかし、本来の暑気払いは「無理に参加する場」ではなく、夏の疲れを労い、感謝を伝えるための時間です。
たとえば、普段は話す機会が少ない他部署との交流ができたり、上司や部下との関係性が深まるきっかけにもなります。ちょっとした差し入れや軽い会話でも、「ありがとう」の気持ちが伝わる場として機能することも多いです。
無理なく、気軽に参加できる雰囲気をつくることで、コミュニケーションの活性化やチームビルディングにもつながるのが暑気払いの良いところ。また、業務的な打ち上げではなく「ねぎらい」の意味が込められた行事として考えると、季節の区切りとして気持ちよく夏を迎えるためのよいタイミングにもなります。
暑気払いの本来の意味を知って、気持ちよく開催しよう
暑気払いは、ただの飲み会ではなく、夏を健やかに過ごすための日本らしい風習です。その由来や意味を知ることで、職場や仲間内での開催もより意義あるものになるはずです。
年々暑さも厳しくなっているので、形式にとらわれすぎず、気軽に夏の労をねぎらう場として開催すれば、コミュニケーションの活性化やチームの一体感づくりにもつながります。心も体もリフレッシュできる暑気払いで、夏を元気に乗り切りましょう!
暑気払いの案内や挨拶、などは以下の記事も参考にしてみてください。