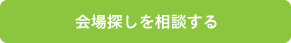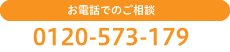宴会の幹事を頼まれたら?挨拶の順番決め・段取り・マナー
2021/5/17
2023/06/06
宴会の幹事を任されたら、間違えてはいけないのは挨拶の順番決めと、段取りです。 この記事では、宴会の幹事のあなたに向けて、宴会の挨拶の順番決めと段取りのコツ、挨拶に関連する宴会マナーについてご紹介します。
Contents
宴会の挨拶順番決めと段取りのコツ
宴会の幹事をすることになったら、会費や予算配分を決め、記念品や花束を手配したり、宴会日時と場所を確定させ、会場を手配したり、参加者の出欠を確認したりなど、大忙しです。 中でも、一番大切なのは宴会の挨拶の順番を決めることです。 宴会というものは、人の集まり、コミュニティの単位で開かれます。
そもそも、宴会は、単にコミュニケーションの場ではなく、人との出会いや別れ、節目にあわせて、コミュニティの結束などを確認するため、開かれるものなのです。 その宴会の中で行う挨拶の順番は、そのままコミュニティの序列を表すため、決めるときは配慮が必要です。
つまり、挨拶の順番=偉い人のランク付けになるので、間違えると大変失礼にあたります。 そのため、ちゃんと宴会の挨拶の順番決めの基本ルールを知った上で、行うことをおすすめします。
宴会の挨拶の順番決めの基本ルール
宴会の挨拶の順番決めの基本ルールは「宴会の主賓が決まったら、挨拶の順番を決める」です。 主賓(しゅひん)とは、その宴会の主役のこと。 わかりやすい例で言えば、誕生日会では誕生日を迎える人が主役で、主賓です。
同様に、新人歓迎会であれば、歓迎される新人が主賓で、送別会であれば、送られる人が主賓です。懇親会のような定例のコミュニケーションを目的とした宴会では、特に主賓が設定されないこともありますが、その場合はその集まりで一番偉い人が主賓を何かしらの理由で指定することが多いようです。
主賓を決めてから、挨拶の順番を決める理由は、主賓に近い所属の偉い人が、挨拶をすることになるからです。 通常、宴会には、次のような流れがあり、その都度、挨拶があります。 ちなみに「本締め」は、司会進行が閉会を告げる前に、簡単なスピーチをし、一本締めなどの手締めを行う挨拶の一種です。
| 開会(司会進行) 乾杯の挨拶(コミュニティで1番偉い方) 主賓からの挨拶(主賓) 本締め(コミュニティで2番目に偉い方) 閉会(司会進行) |
主賓が誰かによって、本締めの挨拶をする人、つまりコミュニティで2番目に偉い方の位置付けは変わってきます。
例えば、企業の部署単位での送別会なら、コミュニティで1番偉い方である部長が乾杯の挨拶をし、送り出される人の所属する課の課長が本締めの挨拶をすることになります。課長のような、コミュニティで2番目に偉い方が複数いたとしても、宴会の中で課長全員が挨拶をするわけではなく、主賓にあわせて選出することになるのです。
ただし、主賓が複数いる宴会は珍しくありません。主賓が複数いて、所属がばらける場合、本締めとは別に、主賓の挨拶の後で一言いただくようにし、本締めはそこで一言を話さなかった方に依頼する、という方法もあるので、上司などに判断をあおぎながら臨機応変に対応しましょう。
また、コミュニティの序列とは関係なく、主賓と縁の深い人に挨拶してもらいたいなら、主賓の挨拶の直後などに、挨拶してもらうのが妥当です。その時、記念品や花束などを主賓に渡すと、感動的に演出できます。 挨拶の順番決めの例をあげておきます。
| ケース1:ある企業で、部署の課の単位で、宴会を開きます。宴会の名目は送別会です。主賓は一般社員1名です。課の中には2つのチームがあり、主賓はAチームです。 |
- 乾杯の挨拶:課長
- 本締め:Aチームのリーダー または 主賓と縁が深い・親しい人
コミュニティで一番偉い課長が、乾杯の挨拶をします。本締めは、主賓が所属するAチームのチームリーダーなど、次にコミュニティの中で偉い方に打診するのが定番です。主賓その人がチームーリーダーだった場合、主賓と縁の深い後輩社員などでもよいでしょう。 本締めの人選は、地域や世代、社風、そのコミュニティによってかなり判断基準が変わるので、迷ったら、課長に相談したり、ベテラン社員に相談したりするのが一番です。
なお、送別会の段取りのコツ、進行例と司会進行の台本例を知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。 司会兼幹事は必見!送別会の挨拶の順番と進行の台本例
| ケース2:ある企業で、ある部署で、宴会を開きます。宴会の名目は、新人歓迎会です。主賓は新人2名です。部の中にA B と2つの課があり、新人が配属されるのは、A課のみです。 |
- 乾杯の挨拶:部長
- 本締め:A課の課長
コミュニティで一番偉い部長が、乾杯の挨拶をします。本締めは、主賓が所属する事になるA課の課長が妥当です。 もし、新人配属がどちらの課にもされるのであれば、同じランクの課長が複数いることになるため、社歴の長さや年齢を考慮し、序列が上の方が挨拶します。 あるいは「主賓からの挨拶」の後、「本締め」の前に、宴会の中盤で行う締めの「中締め」を追加し、課長のどちらかに依頼する形でもいいでしょう。
- 乾杯の挨拶:部長
- 本締め:A課の課長(B課の課長より序列が上)
- 中締め:B課の課長
ただし、地域や世代、社風、コミュニティによっては、中締めと本締めの序列の意識が異なる人もいるため、詳しい方に判断をあおいでください。 新年会の例ですが、中締めや本締めなど「手締め」について詳しく知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。 新年会で締めの挨拶を頼まれたら?手締めのやり方や文例を紹介
挨拶は事前に依頼する
宴会の挨拶を事前に依頼するのは、もはや常識です。 もし宴会の日時や場所を決める立場にあるなら、主賓を決めた後、最優先で挨拶の順番を確定させましょう。 つい「挨拶の順番決めは、宴会の日時や場所が決まったあとでいいのでは?」と思ってしまいますが、そもそも、主賓と挨拶すべき方が宴会に参加できなければ、コミュニティにとって、宴会があまり意味のないものになってしまいます。 主賓と挨拶すべき方、それぞれに挨拶の依頼をし、そこで都合のよい日時を確認し、重なった時間帯を宴会の日時とするのが、一番賢いやり方と言えるでしょう。
都合のよい日程を確認がてら挨拶の依頼をするのは、メールなどではなく、対面で確認する方が失礼とならないでしょう。それまでにざっくりとコース料理の内容や会場の予定を決めておき、伝えると喜ばれます。
挨拶に関連する宴会マナー
挨拶の後にお礼を添えるときはTPOを見極めて
挨拶を頼んだ方の挨拶が終わったときに「ありがとうございました」と司会進行がお礼の言葉を添えるべきかどうかは、宴会のフォーマル度と、挨拶する方と司会進行の関係性によって変わります。
例えば、新年会のような、企業単位で開くフォーマルな宴会では、司会進行は主催側なので、主催者の立場で挨拶する者への挨拶のお礼は言わず、外部のゲストにあたる方にだけ挨拶のお礼を添えて、進行させるのが通例です。
しかし、部や課単位のフォーマル度が少し落ちる宴会であれば、関係性などは気にせず、挨拶が終わったら「ありがとうございました」と一言添えて、進行するのがよいでしょう。 挨拶の後にお礼を添えるときはTPO(時・所・場合)を見極めましょう。
ご厚志(お志)の感謝を伝えるのは「乾杯の挨拶の後」がベスト
幹事をすると、宴会で会費以外のお金、ご厚志(お志)をいただくこともあります。幹事だけが感謝を伝えるのではなく、宴会の参加者からも感謝を伝える機会があるべきですよね。 通常、乾杯の音頭の後、宴会の参加者に対して、誰からご厚志(お志)をいただいたかを伝えるのが一般的です。なお、金額は伏せます。複数の方からいただいたなら、序列の高い方から順番に紹介しましょう。
まとめ
宴会の中で行う挨拶の順番は、そのままコミュニティの序列を表すため、宴会の挨拶の順番決めは気をつけないといけません。 宴会の挨拶の順番決めの基本ルールは「宴会の主賓が決まったら、挨拶の順番を決める」です。
コミュニティの中で1番偉い方が挨拶するのは変わりませんが、主賓が誰かによって、例えば本締めの挨拶をする人、コミュニティで2番目に偉い方の位置付けは変わります。 また、宴会の挨拶は事前に依頼するのは、もはや常識です。都合のよい日程を確認がてら挨拶の依頼をするのは、対面で確認しましょう。 そつなく宴会の挨拶の順番を決め、スマートに宴会を楽しみましょう!