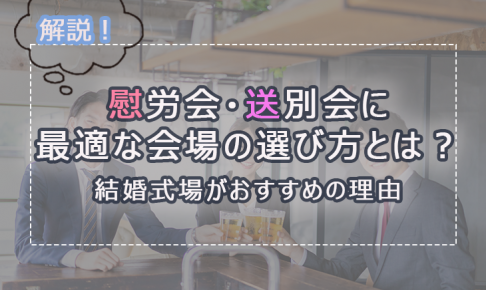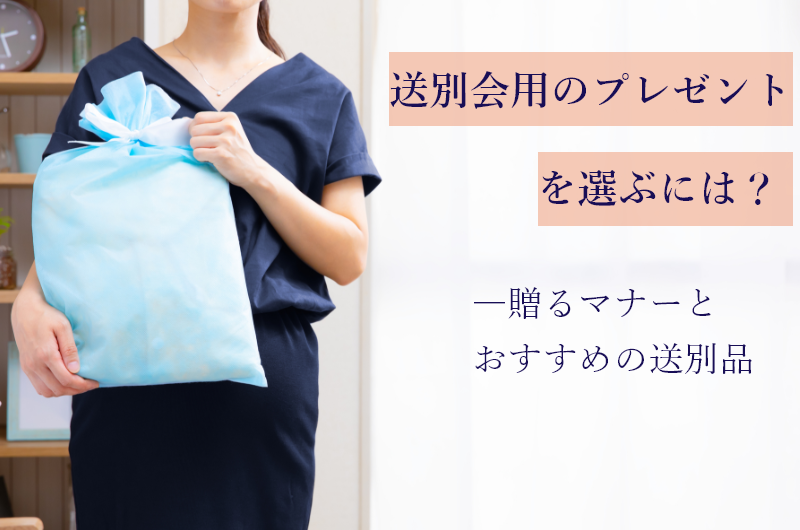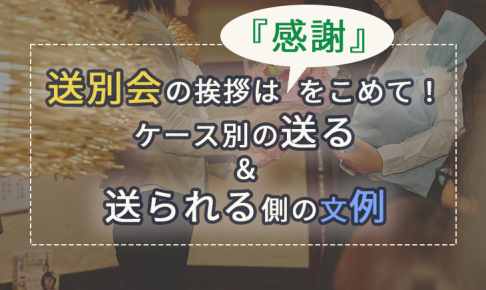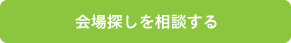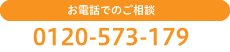送別会の幹事必見!準備や司会進行・挨拶の流れを解説【例文つき】
2020/6/13
2023/04/27
送別会の司会や幹事になったら、会場を予約したり、送別会がうまく進行するようにスケジュールを決めたり、事前にいろいろな準備が必要です。
また、送別会当日の司会進行や挨拶の内容について事前に決めておく必要があるでしょう。今回の記事では、送別会の幹事がやるべき準備や、当日の司会進行の流れ、挨拶の例文について紹介しています。
これから送別会の準備を始める、という幹事の方はぜひ参考にしてください。
Contents
幹事が行う送別会当日までの準備の流れ

画像素材:PIXTA
送別会の幹事になったら、計画的に準備を進めましょう。
|
送別会では、退職者や転出者などの主賓が複数いるケースがあります。主賓の人数をはっきりと把握し、記念品や花束の手配をしましょう。また、送別会では主賓や上司に挨拶を依頼します。挨拶を依頼する相手が出席できる日を事前に確認し、送別会の日程を決めましょう。
送別会の日程が確定したら、確認を含め再度挨拶を依頼しましょう。メールではなく直接依頼すると良いです。

出典:PIXTA
送別会の会費は、記念品や花束を準備する費用を考慮し、飲食代より少し高めに設定します。
参加予定者に、日時と会費を伝えて出欠をとりましょう。
会場はできるだけ職場から近く、駅からのアクセスが良い場所を選びます。二次会を予定している場合は、一次会の会場から近い場所でいくつか候補を探しておきましょう。
会場選びのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
幹事が知っておきたい送別会を成功させる4つのポイント

画像素材:PIXTA
送別会を成功させるために、幹事が知っておきたい4つのポイントを紹介します。それぞれのポイントをおさえて、素敵な送別会を開催しましょう。
|
司会の台本を作成しておく
送別会の流れに沿って、タイムススケジュールが分かる司会の台本を作成しておきましょう。挨拶を依頼する人の名前や司会のセリフを具体的に記載した台本を作成しておくことで、歓迎会当日に流れを忘れずに進行できます。
作成する台本のタイムスケジュールは、会場の利用可能時間を考慮して作成します。また、挨拶を依頼する人の氏名は、フリガナを振っておくと読み間違えがなく安心です。
挨拶の依頼を忘れずにしておく
送別会では、乾杯の挨拶や退職する人から、複数の場面で挨拶をしてもらうでしょう。幹事になったら、挨拶の依頼をできるだけ早い段階でしておきましょう。また、誰にどの挨拶を依頼するか、マナーを把握しておくことも大切です。
| 乾杯の挨拶 | 直属の上司や参加者の中で一番役職が高い人 |
| 送る言葉 | 直属の上司や関わりが深い同僚 |
| 本締めの挨拶 | 参加者の中で2番目に役職が高い人 |
二次会の有無を事前に決めておく
二次会の有無は、送別会の準備を進める段階で決めておきましょう。会社の先輩や前回幹事をした人に、これまでの送別会で二次会を行ったかどうかを聞き、参考にすると良いです。
二次会の会場は、一次会の会場から移動しやすい場所を選びましょう。
翌日以降に参加者にお礼をする
送別会が終わったら、翌日以降に出来るだけ早く参加者にお礼の連絡をしましょう。お礼の連絡はメールで構いません。送別会の会費で余剰金が出た場合や、二次会の会費の清算が必要な場合は、メールに記載します。
|
送別会当日の進行

画像素材:PIXTA
送別会当日は、幹事が進行を執り行うことがほとんどです。進行の流れを確認しておきましょう。
|
送別会で送られる主賓を囲んで、食事と歓談を楽しみましょう。
本締めは、閉会する前に司会が行う挨拶です。閉会を告げる前に、主賓へのスピーチ行い、一本締めなどの手締めを行います。
閉会後は、スムーズに会場を出られるように、事前にお会計をすませておきましょう。
送別会での挨拶・司会の流れと例文

画像素材:PIXTA
送別会では、送る側と贈られる側が挨拶をする場面がいくつかあります。幹事や司会が始まりの挨拶や開会の挨拶を行います。乾杯の挨拶や送る側の挨拶を役員や上司が行う場合は、必ず事前に依頼しておきましょう。
また、主賓である贈られる側からの挨拶も、事前に依頼しておくことがマナーです。
送別会の流れに沿って、司会・挨拶の例文とポイントを確認しておきましょう。
開会の挨拶
退職する人と、司会を行う自分自身の紹介を含めて開会の挨拶をします。
|
本日はお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。 それでは、これより【送別会の名前 (例:Aさんの送別会)】をはじめます。最後までどうぞお楽しみください。 |
乾杯・代表の挨拶
乾杯の挨拶は、送別会に参加する人の中で最も役職が高い人に依頼します。退職者の直属の上司や役員などに依頼しましょう。
|
では、乾杯の音頭を【乾杯の音頭をとる者の氏名】さんにお願いします。 各自グラスの用意をお願いします。 ※ スピーチ後に乾杯する |
乾杯のスピーチについての詳しい解説や例文は、以下の記事で紹介しています。
食事の開始
乾杯の挨拶の直後に、司会は食事開始の案内をします。
食事や歓談の時間は50~60分を目安に確保しておきましょう。コース料理の場合、デザートが出てくる時間までを目安にします。幹事は、食事や歓談中に参加者の飲みものや食事がいきわたっているか、足りないものがないかなどに目を配りましょう。
|
それでは、みなさま、しばらくの間、お食事とご歓談をお楽しみください。 |
送る側の挨拶
送る側の挨拶は、退職者の直属の上司や関わりが深い同僚などに依頼します。司会は、歓談中の参加者に声をかけ、挨拶をする人に注目させることが大切です。
| みなさま、お食事中ご歓談中ではございますが、ここで【送る側の挨拶をする者の氏名】さんからご挨拶をいただきます。 |
送る側の挨拶の詳しい解説や例文は以下の記事で紹介しています。
プレゼント・花束の贈呈
送る側の挨拶が終わったら、主賓である退職者や転出者にプレゼントや花束を贈呈しましょう。退職する人の部下や同僚に贈呈を依頼しておくと良いです。プレゼントや花束は、すぐに取り出せる場所に準備しておきましょう。
|
【送る側の挨拶をする者の氏名】さん、ありがとうございました。退職される【主賓の氏名】さんに、チーム一同より記念品と花束を用意しました。【贈呈する者の氏名】さん、よろしくお願いします。 ※プレゼントや花束の贈呈 |
送別会のプレゼントの選び方のポイントは以下の記事で解説しています。
退職者側の挨拶
プレゼントや花束の贈呈直後に、退職者からの挨拶をしてもらいましょう。
飲み物や食事のラストオーダーの時間が決まっている場合は、参加者に知らせておきます。
|
【主賓の氏名】さん、最後にご挨拶をお願いします。 ※主賓の挨拶 【主賓の氏名】さん、ありがとうございました。 それではみなさま、引き続きご歓談をお楽しみください。また、飲み物のラストオーダーが20時となっております。ご注文される方は、20時までにお声かけください。 |
送別会での退職者の挨拶の例文は以下の記事で紹介しています。
本締めの挨拶
送別会終了の前に、本締めの挨拶を行います。参加者の中で2番目に役職が高い人に依頼しましょう。
閉会後にスムーズに会場を出るために、本締めの挨拶の前にお会計を済ませておくと良いです。
|
宴もたけなわではございますが、そろそろお時間がまいりましたので、締めの挨拶を【本締めの挨拶をする者の氏名】さんにお願いいたします。 【本締めの挨拶をする者の氏名】さん、よろしくお願いいたします。 ※ 一本締めなどを行う ありがとうございました。 |
閉会の挨拶
本締めの挨拶が終わったら、そのまま司会が閉会の挨拶をします。二次会がある場合は、会場までの移動を促しましょう。
|
【送別会の名前】はこれにて、お開きとさせていただきます。 まだまだ話したりないという方は二次会もご用意していますので、ふるってご参加ください。 お帰りの方はお気をつけてお帰りください。 お忘れ物のないようにご注意ください。 みなさま、本日はお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございました。 |
幹事が知っておきたい送別会を成功させる4つのポイント

画像素材:PIXTA
送別会を成功させるために、幹事が知っておきたい4つのポイントを紹介します。それぞれのポイントをおさえて、素敵な送別会を開催しましょう。
|
司会の台本を作成しておく
送別会の流れに沿って、タイムススケジュールが分かる司会の台本を作成しておきましょう。挨拶を依頼する人の名前や司会のセリフを具体的に記載した台本を作成しておくことで、歓迎会当日に流れを忘れずに進行できます。
作成する台本のタイムスケジュールは、会場の利用可能時間を考慮して作成します。また、挨拶を依頼する人の氏名は、フリガナを振っておくと読み間違えがなく安心です。
挨拶の依頼を忘れずにしておく
送別会では、乾杯の挨拶や退職する人から、複数の場面で挨拶をしてもらうでしょう。幹事になったら、挨拶の依頼をできるだけ早い段階でしておきましょう。また、誰にどの挨拶を依頼するか、マナーを把握しておくことも大切です。
| 乾杯の挨拶 | 直属の上司や参加者の中で一番役職が高い人 |
| 送る言葉 | 直属の上司や関わりが深い同僚 |
| 本締めの挨拶 | 参加者の中で2番目に役職が高い人 |
二次会の有無を事前に決めておく
二次会の有無は、送別会の準備を進める段階で決めておきましょう。会社の先輩や前回幹事をした人に、これまでの送別会で二次会を行ったかどうかを聞き、参考にすると良いです。
二次会の会場は、一次会の会場から移動しやすい場所を選びましょう。
翌日以降に参加者のお礼をする
送別会が終わったら、翌日以降に出来るだけ早く参加者にお礼の連絡をしましょう。お礼の連絡はメールで構いません。送別会の会費で余剰金が出た場合や、二次会の会費の清算が必要な場合は、メールに記載します。
まとめ

画像素材:PIXTA
送別会の幹事になったら、司会の台本を作成して、乾杯の挨拶や送別の挨拶を依頼する人を決めましょう。挨拶を依頼する場合は、出来るだけ早い段階で声をかけることが大切です。
今回ご紹介した例文を参考にして、送別会をスムーズに進めるための台本を作成する参考にしてください。
また、送別会が終わったら、参加者や挨拶を担当してくれた方へのお礼メールを忘れずに送るようにしましょう。