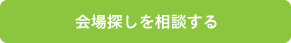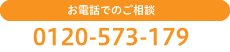【セリフ例付き】懇親会の司会テンプレート 役割からマナー、心構えを解説
2025/7/17
懇親会の司会を任されて、「どうやって進行すればいいの?」「なにを話せばいいの?」と不安を感じていませんか?
本記事では、懇親会の基本的な進行の流れや実際に使える台本セリフ、司会前に確認しておきたいポイント、マナーやNG例までをわかりやすく解説します。準備をしっかり整えれば、はじめての司会でも大丈夫。参加者にとって心地よい時間をつくるお手伝いができるよう、安心して進められるヒントをお届けします。
Contents
懇親会の司会の役割と幹事との違いについて
懇親会を円滑に進めるためには、司会と幹事それぞれの役割を正しく理解し連携することが大切です。一見すると似たような役割に見えますが、担っている内容は大きく異なります。
| 幹事 | 企画や準備を担当する裏方的な役割 |
| 司会 | 当日の進行を行う表の役割 |
幹事は、懇親会の全体を企画し事前の準備を担当します。会場の手配や出欠確認、進行スケジュールの作成など開催に向けた段取りを整えるのが主な仕事です。一方で司会は、当日の進行を担い、参加者に向けてスムーズに会を進めていく“顔”のような存在です。
たとえば、幹事が「開会のあいさつ」や「乾杯の音頭」を誰にお願いするかを事前に決め、司会に伝えておくことで当日はスムーズな流れになります。あらかじめ情報をすり合わせておくことで司会は迷わず進行でき、会全体の安心感にもつながります。
初めて司会を担当する方にとっては緊張もあるかもしれませんが、幹事と連携しておけば心強い味方になります。役割の違いを理解し、しっかりと準備を共有しておくことが懇親会成功のポイントとなります。
懇親会の司会の基本的な進行プログラム
懇親会の司会をスムーズに進めるためには、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが重要です。基本的な進行パターンを把握しておくことで、焦ることなく安心して役割を果たすことができます。
一般的な懇親会の進行は、以下のような流れで行われます。
【懇親会の一般的な流れ】
|
会の目的や規模によって進行内容が多少異なる場合もありますが、上記のような流れが基本です。
事前に幹事や主催者と進行内容を確認し、誰がどのタイミングで話すのかを把握しておきましょう。参加者が快適に過ごせるよう時間配分にも気を配り、各パートのタイミングを意識することで自然でスマートな進行が実現します。
懇親会司会の台本テンプレートとセリフ例
司会が初めての方にとって、当日の進行は緊張するものです。
そんなときに役立つのが進行の流れに沿った台本やセリフのテンプレートです。あらかじめ話す内容を決めておくことで余裕を持って進行でき、参加者にも安心感を与えることができます。
ここでは、懇親会の一般的な進行にあわせて、司会のセリフ例を前半・中盤・後半に分けてご紹介します。実際に使えるフレーズを押さえておけば、自信を持ってマイクを持つことができるはずです。
前半パート:開会のあいさつ〜乾杯まで
懇親会の冒頭では、場の雰囲気を整え、参加者をスムーズに会の流れへと導くことが司会の役割です。開会のあいさつから乾杯までの間に上司や主催者の紹介も含まれるため、事前に登壇者の名前や順番を確認しておくことが大切です。
なお、前半パートでは会の「はじまりの空気」を整えることが最も大切です。丁寧な言葉遣いを心がけ、安心して参加してもらえるような雰囲気づくりを意識しましょう。
開会の挨拶(例)
| 「みなさま、本日はお忙しいなかご参加いただき、誠にありがとうございます。ただいまより○○部主催の懇親会を開催いたします。本日の司会を務めます、○○です。どうぞよろしくお願いいたします。」 |
主催者・上司のあいさつ紹介(例)
| 「まずは、○○部 部長 ○○より、ごあいさつをいただきます。○○部長、お願いいたします。」 (※あいさつ終了後) 「○○部長、ありがとうございました。」 |
乾杯の発声の案内
| 「続きまして、乾杯のご発声を、○○株式会社 取締役 ○○様にお願いしたいと思います。○○様、よろしくお願いいたします。」 (※乾杯後) 「ありがとうございました。それでは、しばしご歓談をお楽しみください。」 |
中盤パート:歓談中のアナウンスや余興の案内
懇親会の中盤は、参加者同士の交流が深まる歓談タイムが中心です。基本的には自由に過ごしてもらう時間ですが、必要に応じて案内やお知らせを入れることで、全体の流れが乱れずスムーズな進行につながります。
中盤パートでは、あくまでも場の流れを壊さないようにやさしく声をかけるスタンスがポイントです。タイミングや声のトーンにも気を配ると、自然な進行ができます。歓談中に行う余興や企画がある場合は、その前に一言アナウンスを入れるようにしましょう。
歓談開始時のアナウンス
| 「それでは、ここからはご歓談の時間となります。お食事やお飲み物を楽しみながら、皆さま同士でご交流をお楽しみください。」 |
余興・ゲームがある場合の案内
| 「このあと○時より、ささやかながら余興をご用意しております。皆さまで楽しんでいただければと思いますので、お時間になりましたら前方にご注目ください。」 |
時間の進行アナウンス(中締め前など)
| 「そろそろお時間が近づいてまいりましたので、お飲み物などお手元にご準備のうえ、お待ちいただけますと幸いです。」 |
後半パート:中締め〜閉会のあいさつ
懇親会の後半では、中締めやお開きのあいさつを通じて、会を気持ちよく締めくくることが司会の役割となります。
終わりの雰囲気をうまくつくることで、参加者にとっても印象深い会になります。最後まで丁寧に進行することで、懇親会の印象がぐっと良くなります。笑顔を忘れず、しっかりと締めくくりましょう。
中締めのあいさつのご案内
| 「名残惜しいところではございますが、そろそろ中締めのお時間となりました。ここで○○部 課長 ○○より、ごあいさつをいただきます。○○課長、よろしくお願いいたします。」 (※あいさつ後) 「○○課長、ありがとうございました。」 |
締めのあいさつ(上司や参加者代表などが行う場合)
| 「続きまして、締めのごあいさつを○○株式会社 部長 ○○様よりいただきます。○○様、よろしくお願いいたします。」 (※あいさつ後) 「○○様、ありがとうございました。」 |
閉会のあいさつ
| 「以上をもちまして、本日の懇親会はお開きとさせていただきます。皆さま、本日はご参加いただき誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。」 |
二次会のご案内(ある場合)
| 「このあと、○○にて二次会を予定しております。ご都合の合う方はぜひご参加ください。」 |
司会前に確認しておくべきこと
懇親会の司会を成功させるためには、事前の準備が大きな鍵を握ります。当日の流れや登場人物、必要な備品などを事前にチェックしておくことで、落ち着いて進行に臨むことができます。
司会は「アドリブ力」よりも「段取り力」がものを言うポジションです。小さな確認の積み重ねが、大きな安心感につながります。
【司会前に確認しておきたい主なポイント】
| □ 進行内容の確認 | 誰がいつ話すのか、登壇者や乾杯・中締めの担当者の順番などを明確にしておきましょう。 |
| □ 登壇者の氏名・役職の読み方チェック | 呼び間違いは失礼にあたるため、正確にメモしておくと安心です。 |
| □ マイク・音響の使用方法 | 会場の設備を事前に確認し、マイクの位置や使い方に慣れておきましょう。 |
| □ タイムスケジュールの把握 | 予定より早く進む・遅れる可能性も考慮して、柔軟に対応できるよう意識しておくことが大切です。 |
| □ 台本や進行メモの準備 | 頭の中だけで覚えるより、紙やスマートフォンなどにメモを用意しておくと、安心して進行できます。 |
準備をしっかり行っておくことで、当日も落ち着いて司会を務めることができます。特に初めて司会を任される場合は、「確認しすぎなくらいでちょうどいい」と思っておくと良いでしょう。
懇親会の司会で気をつけたいマナーやNG例
懇親会の司会では、基本の進行だけでなく「言葉遣い」や「気配り」などのマナーも大切です。せっかく準備をしていても、ちょっとしたひと言や態度が参加者の印象を左右することもあるため、場にふさわしい振る舞いを意識しましょう。
また、やってしまいがちなNG例も紹介します。安心して司会を務められるように確認しておきましょう。
懇親会の司会で気を付けておくべきマナー
懇親会の司会では、話し方や所作ひとつで参加者の印象が大きく変わることがあります。
話す内容だけでなく、「どんな態度で話すか」にも注意を払うことで、より丁寧で信頼感のある進行ができます。以下のような基本的なマナーを意識しておくと、安心して司会を務めることができます。
言葉遣いは丁寧に、敬語を基本に
上司や来賓がいる場合は、親しみやすさよりも礼儀正しさを優先しましょう。
落ち着いた声とスピードで話す
緊張して早口になりがちですが、ゆっくり丁寧に話すことで、聞き手にも安心感を与えます。
参加者への気配りを忘れずに
歓談中の声かけや、余興・中締めのアナウンスなども、やわらかく丁寧に行うのがポイントです。
懇親会で司会をする際に避けたいNG例
いくら準備をしていても、ちょっとした一言や振る舞いがマイナス印象につながることがあります。
特に「うっかりやってしまいがちな失敗」は、事前に意識しておくことで防ぐことができます。
氏名や役職の読み間違い
事前に登壇者の名前と役職をしっかり確認し、メモしておくことが重要です。
お酒に関する過剰なネタ・下ネタ
場を盛り上げようとしても、不快に感じる人がいるため、冗談のラインには注意が必要です。
私語が多い、私的な話に偏る
進行中に自分の話を挟みすぎると、司会の立場がブレてしまいます。あくまでサポート役に徹しましょう。
懇親会で司会をするときの心構え
懇親会の司会と聞くと、「人前で話すのは苦手…」「盛り上げられるか不安」と感じる方も多いかもしれません。しかし、懇親会の司会は特別なスキルや経験がなくても、ちょっとした心構えがあればしっかりと務めることができます。
懇親会の司会は「主役」ではなく、「場を整えるサポーター」のような存在です。自分が前に出すぎず、参加者が気持ちよく過ごせるような進行を意識しましょう。
また、すべてを覚えようとせずに、進行メモや台本を手元に用意することも大切な準備のひとつです。「緊張するのが当たり前」と割り切りつつ、笑顔と落ち着きで進めていけば、会全体の印象もぐっと良くなります。
懇親会の司会は準備を整えて安心して進行しましょう
懇親会の司会は、会の雰囲気をつくり、参加者の交流を支える重要な役割です。はじめて任されると緊張するかもしれませんが、事前に流れを把握し、準備を整えておけば、誰でも安心して進行できます。
今回ご紹介した「進行の流れ」や「台本例」、「マナーや注意点」を参考にすることで、場にふさわしい進行ができるはずです。
完璧を目指す必要はなく、誠実で丁寧な進行を心がけることが何より大切です。
落ち着いた声でゆっくり話し、笑顔を忘れずに。準備の積み重ねが自信につながり自然と会場の雰囲気も和らぎます。あなたの司会が、参加者にとって心に残る懇親会をつくる一助となりますように。
【関連記事】