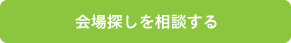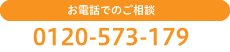【コピペOK】歓迎会の締めの挨拶まとめ 中締め・本締めの文例をシーン別に紹介
2025/8/25
歓迎会の締めの挨拶を任されたけれど、「何を話せばいいかわからない」「中締めと本締めってどう違うの?」と悩んでいませんか?
実は、締めの挨拶にはシーンに応じたコツとマナーがあり、少しの工夫で印象が大きく変わります。
本記事では、中締め・本締めそれぞれの目的や違いをわかりやすく解説しつつ、フォーマル・カジュアルな場面別に使える文例を豊富にご紹介します。
また、ChatGPTなどのAIを使って挨拶文を作成する際の注意点や依頼のコツも紹介していますので参考にしてみてください。
Contents
歓迎会の締めの挨拶の基本の流れ
歓迎会の締めの挨拶とは、その場をしめくくる役割を担うスピーチであり、主賓への歓迎の気持ちをあらためて伝えるとともに、会の参加者に感謝を伝えて気持ちよく会を終えるための大切なひとことです。スムーズな進行のために、以下の流れを意識して挨拶を組み立てると安心です。
【締めの挨拶・基本の構成(例)】
|
1.導入の挨拶 2.主賓への歓迎の言葉 3.会の内容へのひとこと(任意) 4.締めの言葉・今後への一言 5.手締めや挨拶の締めくくり |
また、締めの挨拶には「中締め」か「本締め」という違いがあることも事前に確認しておくと安心です。
- 中締め:会の途中、上司の退席などのタイミングで行う
- 本締め:会のラストを締める挨拶
どちらに該当するかで、挨拶の内容やトーンも少し変わってきます。幹事に事前確認をしておくことが大切です。基本の流れを押さえたうえで場に合った内容を意識することが、印象の良い締めの挨拶につながります。
次のセクションでは、挨拶で意識すべき具体的なポイントを見ていきましょう。
歓迎会の締めの挨拶で意識すべきポイント
締めの挨拶は、参加者全体の空気を整え、会を心地よく締めくくるための大切な役割です。歓迎の気持ちと感謝を簡潔に伝えることで、好印象を残すことができます。
特に意識したいポイントは以下の3つです。
シンプルで端的にまとめる
締めの挨拶で一番避けたいのは、「長すぎてダレること」です。会の終盤にあたるタイミングでは、参加者の集中力も落ちてきています。そんな中で話が長くなると、せっかくの歓迎ムードが台無しになる可能性もあります。
目安は1〜2分程度、長くても3分以内。内容を盛り込みすぎず、伝えたいポイントに絞って話すのが好印象につながります。
また、事前にメモを用意したり、話す順序(導入 → 歓迎 → 今後への期待 → 締め)を決めておくと安心です。緊張して早口になりがちなので、「ゆっくり話す」ことを意識すると落ち着いた印象になります。
TPOに合わせた言葉選びをする
締めの挨拶は、ただ形式的に終わらせるだけでなく、「その場にふさわしい言葉で伝えること」が大切です。
どんなに内容が良くても、フォーマルな場でカジュアルすぎる言葉を使えば違和感を与えてしまいますし、逆に親しい集まりで堅苦しすぎると場がしらけてしまうこともあります。
イベントの目的・参加者の顔ぶれ・関係性を意識して、適切なトーンに調整しましょう。「ビジネスの場での丁寧さ」と「カジュアルな場での親しみやすさ」のバランスがポイントです。
| シーン | 特徴 | トーン例 |
| 社内のフォーマルな歓迎会 | 上司や経営層が参加 | 丁寧で敬意のある言葉遣いを意識 |
| カジュアルな部署単位の会 | 同期や親しいメンバー中心 | 少しくだけた表現やユーモアもOK |
| 保護者会・地域の懇親会 | 年齢層が幅広い | 温かく、簡潔で伝わりやすい表現を意識 |
このように「誰に、どんな場面で話すか」を考えるだけで、挨拶の印象は大きく変わります。迷ったときは、少しフォーマル寄りにしておくと無難です。
手締めがある場合は進行も意識する
手締めは、「この場を無事に終えましょう」「ありがとうございました」などの意味を込めて手を打つ儀式的な動作です。一本締めや三本締めなどが手締めに該当します。
手締めは締めの挨拶とセットで任されることがあるため、あらかじめ進行を確認しておくとスムーズです。手締めには地域差や慣習があるため、「どの手締めにするか」は幹事と事前に確認しておきましょう。
【よく使われる手締めの種類】
|
・一本締め ・三本締め ・関東一本締め(いわゆる“いっちょうじめ”) |
なお、手締めを担当する場合は、「それでは○○締めで締めさせていただきます」といった一言を添えることで、場の空気をうまくまとめることができます。
歓迎会の締めの挨拶 文例集
ここからは、実際に使える締めの挨拶の文例をご紹介します。挨拶の内容は、「中締め」か「本締め」かによって目的も雰囲気も変わります。
それぞれのシーンに合った文例を参考に、自分に合ったスタイルで調整してみてください。
中締めの挨拶例文(途中退席者がいる場面など)
中締めは、会の途中で一区切りをつけるための挨拶です。たとえば、上司や来賓が退席するタイミング、あるいは会の前半と後半を分けたい場面などで行われます。
会自体はまだ続くため、あくまで「場を崩さず、切り替えるための挨拶」が求められます。主賓や退席者への感謝を伝えつつ、その後も続く場の空気を大切にすることがポイントです。
フォーマルな歓迎会(上司・経営層が参加)
|
皆さま、本日はご多用のところお集まりいただき、誠にありがとうございます。 ここで一度、中締めとさせていただきます。本日ご参加いただいた◯◯部長には、この後ご予定があるとのことで、ここでご退席されます。 お忙しい中、温かいお言葉をいただき、ありがとうございました。 引き続き、皆さまでご歓談をお楽しみください。 |
カジュアルな社内歓迎会(部署単位・同期など)
|
本日はお集まりいただき、ありがとうございます! このあたりでいったん中締めとさせていただきますが、時間のある方はこのあとも引き続き楽しんでくださいね。 ◯◯さん、これから一緒に働けるのが楽しみです。今後ともよろしくお願いします! |
若手社員・後輩が締めを担当する場合(短め)
|
皆さん、今日はありがとうございます! このあともまだ会は続きますが、ひとまずここで中締めとさせていただきます。 ◯◯さん、これからよろしくお願いします! |
保護者会・地域コミュニティなどカジュアルな集まり
|
本日はご参加いただき、ありがとうございます。 ここでいったん区切りとさせていただきますが、残れる方はこのあともぜひお話ししながら交流を深めていただければと思います。 ◯◯さん、これからどうぞよろしくお願いいたします。 |
本締めの挨拶文例(会を終える場面)
本締めは、会全体の締めくくりとして行う最終的な挨拶です。主賓への歓迎と、参加者への感謝をしっかりと伝えることが目的となります。
場の雰囲気をきれいにまとめ、参加者が心地よく帰路につけるよう、シンプルでメリハリのある言葉選びを意識しましょう。また、必要に応じて一本締めなどの進行を引き受ける場合もあるため、段取りを頭に入れておきましょう。
フォーマルな歓迎会(上司・経営層が参加)
|
本日はお忙しい中、◯◯さんの歓迎会にご参加いただき、誠にありがとうございました。 あらためまして、◯◯さんをお迎えできたことを、心よりうれしく思っております。 今後のご活躍を期待するとともに、皆さまと協力して良いチームを作っていければと思います。 それでは、一本締めで締めさせていただきます。皆さま、お手を拝借── パン! |
カジュアルな社内歓迎会(部署単位・同期など)
|
皆さん、本日はありがとうございました! ◯◯さんがチームに加わってくれて、本当にうれしいです。 明日からまた一緒にがんばっていきましょう! それでは一本締めで締めたいと思います。お手を拝借── パン! |
若手社員・後輩が締めを担当する場合(短め)
|
本日はありがとうございました! ◯◯さんと一緒に働けるのが楽しみです。 簡単ではありますが、これをもちまして締めの挨拶とさせていただきます。 |
保護者会・地域コミュニティなどカジュアルな集まり
|
本日はご参加いただき、ありがとうございました。 ◯◯さんをお迎えできて、とても温かい時間を過ごすことができました。 これからどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、これにてお開きとさせていただきます。 |
歓迎会の締めの挨拶文をAIで作るときの注意点と活用法
最近では、ChatGPTなどのAIを使って、挨拶文を手軽に作成する人も増えています。ChatGPTなどのAIを使えば、挨拶文を短時間で作ることができます。
とはいえ、そのまま読み上げると違和感を与えてしまうケースも多いため、使い方にはコツがあります。
依頼の仕方を工夫すると、精度がグッと上がる
AIに挨拶文をお願いするときは、「できるだけ具体的な情報を伝える」ことがポイントです。あいまいな依頼では、一般的すぎてその場に合わない文章になりがちです。
【依頼時に伝える5つのポイント】
- 誰に向けた挨拶か(例:新しく配属された◯◯さん)
- どんなイベントか(例:部内のカジュアルな歓迎会)
- 話す人の立場(例:若手社員・人事担当・上司など)
- トーンの希望(例:フォーマル/くだけた感じ)
- 長さの目安(例:1分程度、200〜300文字)
【依頼例】
|
営業部に新しく加わった◯◯さんの歓迎会で、若手社員として締めの挨拶をします。 1分くらいで、親しみやすさと感謝を伝えたいです。一本締めも自分で進行します。 フォーマルすぎないトーンでお願いします。 |
このように具体的に伝えることで、AIはより自然で場にフィットした文を出してくれます。
内容をそのまま使わず、必ず確認・調整をする
AIが作った文はベースとしては優秀ですが、「読み上げる用」には微調整が必要です。
内容の正確さや話し言葉としての自然さに注意しましょう。
また、AI文は整っていますが、どこかよそよそしさを感じさせることもあります。
「今日お会いできて本当にうれしかったです」など、自分の感情が伝わる一文を添えるだけで、ぐっと印象がよくなります。
【確認するポイント】
|
・表現がTPOに合っているか ・固有名詞・役職・社名の誤り ・長すぎる・読みにくい表現がないか |
まとめ:歓迎会の締めの挨拶は、気持ちを込めてシンプルに
歓迎会の締めの挨拶は、必ずしも特別なスキルが必要なわけではありません。
大切なのは、「歓迎の気持ち」と「感謝の気持ち」をシンプルに、誠実に伝えることです。
事前に挨拶の流れやポイントを整理し、自分の立場や会の雰囲気に合わせた言葉を選ぶことで、自然で印象の良い締めくくりができます。
また、ChatGPTなどのAIを活用すれば、挨拶文の下書きづくりもスムーズになります。
ただし、依頼の仕方や表現のチェックを忘れずに。最後に「自分の言葉」を少し添えるだけで、グッと心のこもった挨拶になりますよ。
「締めの挨拶なんて緊張する…」という方も、今回ご紹介した文例やポイントを参考にすれば、安心して役目を果たせるはずです。
ぜひご活用ください!