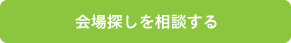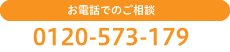忘年会の司会進行のやり方とは?基本の流れと司会の例文、進行のコツを解説
2025/9/18
忘年会の司会は、会をスムーズに進行し、参加者全員が安心して楽しめるようにする重要な役割です。本記事では、開会から閉会までの基本の流れとシーン別の例文を紹介します。さらに、当日までにしておく準備や成功のコツも解説。初めて司会を任された方でも自信を持って進行できるように、ポイントをわかりやすくまとめました。
Contents
忘年会司会の役割と基本の流れ
忘年会の司会は、参加者全員が楽しく過ごせるように会をスムーズに進行する大切な役割です。司会がしっかりと進行をリードすることで、会の雰囲気が引き締まり、参加者も安心して楽しむことができます。
一般的な忘年会の流れは、次のようになります。
|
この流れを頭に入れておくだけで、司会進行の全体像がつかめます。特に、参加者のテンションが上がる「乾杯」や「余興」、会を整える「締め」などの場面は、司会の声かけ次第で雰囲気が大きく変わります。
忘年会当日までに司会が準備しておくこと
司会進行をスムーズに行うためには、当日を迎える前にしっかりと準備を整えておくことが欠かせません。準備不足のまま当日を迎えると、進行が滞ったり雰囲気が崩れたりする原因になってしまいます。ここでは、司会が事前に押さえておきたい準備のポイントをご紹介します。
あいさつをする人の役職・名前を確認
社長や上司の名前、役職を正しく呼ぶことは基本中の基本です。読み間違いや言い間違いは失礼にあたるため、事前にきちんと確認しておきましょう。
特に初めて司会を担当する場合は、フルネームや正式な役職を紙に書いて手元に置いておくと安心です。当日までに幹事や人事担当に読み方を確認しておくと失敗を防げます。
幹事や準備をするメンバーと打合せ
余興担当や受付担当など、当日の進行を支えるメンバーと打ち合わせをしておきましょう。誰がどの役割を担うのか共有しておくことで、予期せぬトラブルにも対応しやすくなります。
特に余興や表彰式がある場合は「誰が登場するのか」「景品はどこにあるのか」など細かい段取りを確認しておくとスムーズです。司会一人で抱え込まず、チーム全体で支え合う意識を持つと安心です。
会場・当日の流れを確認して台本を作成
会場のレイアウトや進行表を確認し、どのタイミングでどの挨拶や余興を行うかを整理しておきましょう。大まかな流れを把握して台本を作っておくと、当日も安心して進行できます。
台本はWordやGoogleドキュメントなどで簡単に作成できます。進行の見出し(開会/乾杯/余興…)ごとに区切って、短いセリフをメモしておくと読みやすいです。印刷して手元に置くだけでなく、スマホに保存しておけば不測の事態でも安心です。セリフを丸暗記する必要はありません。「次は○○部長の乾杯」などキーワードを押さえておくだけでも十分です。
忘年会での司会の進行ポイントと例文
忘年会の司会は、会の雰囲気を作る大切な役割です。進行そのものは決して難しいものではありませんが、場面ごとに適切な言葉を添えることで、参加者全員が安心して楽しめます。進行のポイントとシーン別に司会が使いやすいフレーズや例文をご紹介します。
開会
会のスタートは、参加者全員の注目を集める最初のタイミングです。元気よく、簡潔に始めましょう。司会者であることを伝える自己紹介も忘れずに入れてください。
|
皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日司会を担当させていただきます、〇〇です。よろしくお願いします。それでは、これより○○会社の忘年会を始めさせていただきます。どうぞ最後までお楽しみください。 |
上司・社長のあいさつ紹介
司会から上司や社長を紹介するときは、役職と名前をはっきり伝え、参加者全員に聞こえるように声を出しましょう。
|
それではまず、○○社長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 |
社外の方も参加される忘年会の場合は、社名と正式な役職名をつけておくと良いでしょう。社内での忘年会の場合は〇〇社長よりで十分です。
乾杯へのつなぎ
乾杯は会の盛り上がりを作る大切な場面です。紹介はテンポよく行いましょう。
|
ここで、皆さまお待ちかねの乾杯のご発声をいただきたいと思います。本日は○○部長にお願いしております。○○部長、よろしくお願いいたします。 |
歓談中の一言
歓談が始まると、司会の出番は少なくなります。ただし場が静まってしまったときや、料理や飲み物の案内をするときには一言加えると雰囲気が和みます。
|
お料理やお飲み物は十分にございますので、遠慮なくお楽しみください。 |
余興・表彰式の進行
余興や表彰式は、会場全体を盛り上げるチャンスです。登場人物や段取りをしっかり紹介してから進めるとスムーズです。
|
ここからは余興の時間です。まずは○○チームの皆さんにご登場いただきます。会場の皆さま、大きな拍手をお願いいたします! |
時間が押している場合は、事前に決めておいた順番を省略して進める判断も司会の役目です。
締めのあいさつの振り
会の最後を引き締める締めのあいさつは、役職が2番目に高い人が行うのが一般的です。司会はスムーズにバトンを渡しましょう。
|
それでは締めのご挨拶を、○○専務にお願いしたいと思います。○○専務、よろしくお願いいたします。 |
閉会
忘年会の終了を告げる場面です。明るく、簡潔にまとめると好印象です。
|
以上をもちまして、本日の忘年会をお開きといたします。二次会は〇〇に参加される方はご移動をお願いします。本日は最後までありがとうございました。 |
二次会がある場合は二次会の案内もあわせて伝えるようにしましょう。
忘年会司会を成功させるコツ
忘年会の司会は、特別な技術がなくても「基本のコツ」を押さえておけば安心して進められます。会の雰囲気を壊さず、参加者全員が気持ちよく過ごせるように、次のポイントを意識しましょう。
声はハキハキと、姿勢よく
司会の声は会全体の雰囲気を左右します。大きな会場では特に、マイクを通してもはっきり聞こえるように意識しましょう。背筋を伸ばし、落ち着いた姿勢で進行すると信頼感が増します。
余計なアドリブは控える
場を盛り上げたい気持ちから冗談を多く挟むと、かえって進行が長引いたり場の空気を乱したりすることがあります。シンプルに必要な案内をすることを心がけましょう。
タイムキープを意識する
予定よりも時間が押してしまうと、会全体の雰囲気が崩れやすくなります。進行の合間に時計を確認し、必要に応じて余興や歓談の時間を調整するなど、時間配分をコントロールしましょう。
飲みすぎないようにする
司会自身も参加者の一人ですが、進行役として責任があります。お酒を飲みすぎると進行が滞る原因になるため、節度を持って楽しむことが大切です。
まとめ
忘年会の司会は、参加者全員が安心して楽しめるように会をスムーズに進行する大切な役割です。基本の流れを押さえ、当日までにしっかり準備しておけば、特別な経験がなくても落ち着いて進められます。
開会・乾杯・締め・閉会といった節目ごとの一言や紹介をきちんと行うことで、会全体にメリハリが生まれます。また、声をハキハキと出す、時間配分を意識する、飲みすぎないなどの基本的なコツを意識すれば、よりスムーズな進行ができます。
忘年会は一年を締めくくる大切なイベントです。司会進行を丁寧に務めることで、参加者にとって思い出に残るひとときとなるでしょう。