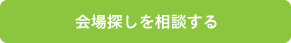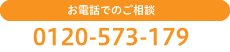忘年会の挨拶で好感度UP!正しい順番と場を和ませる一言・例文集
2025/9/18
忘年会の挨拶は「誰が、どのタイミングで、何を話すか」があらかじめ決まっていることが多く、幹事にとっては重要な準備のひとつです。
本記事では、開会・乾杯・締めの順番や定番の例文、場を和ませる一言アイデアを紹介します。さらに、挨拶をお願いする際の幹事の注意点もまとめました。
忘年会を気持ちよく進行するための参考にしてください。
忘年会の挨拶は誰が担当する?挨拶の基本の順番
忘年会の挨拶は、役職や立場に応じて担当する人がある程度決まっています。あらかじめ順番を把握しておくことで、幹事もスムーズに依頼ができ、参加者も安心して進行を任せられます。ここでは一般的な流れをご紹介します。
開会と閉会の宣言は幹事または司会が一般的
忘年会の始まりと終わりを告げる「開会宣言」「閉会宣言」は、基本的に幹事や司会が担当します。
参加者に対して「これから忘年会を始めます」「本日の会はこれで終了です」とシンプルに伝えるだけで十分です。特に大きな言葉を用意する必要はなく、進行役がしっかりと声を出して伝えることがポイントです。
開会の挨拶は役職が最も高い人に依頼が一般的
開会の挨拶は、その会に出席している中で役職が最も高い人が担当するのが一般的です。
会社の社長や事業部長などがあいさつを行うことで、会全体に重みが出ます。幹事は事前に誰が出席するかを確認し、お願いする相手を決めておくと安心です。
乾杯の挨拶は役職が3番目に高い人に依頼が一般的
乾杯の挨拶は、開会と締めの間をつなぐ役割を担うため、役職が3番目に高い人が担当することが多いです。
トップやNo.2の役職者に比べて少しフランクに話せる立場の方が、乾杯の言葉を盛り上げやすいからです。場の空気を明るくしながら、簡潔に乾杯へと導くのが理想です。
締めの挨拶は役職が2番目に高い人に依頼が一般的
会の最後を締める挨拶は、役職が2番目に高い人が担当することが多いです。
「来年に向けての抱負」「本日の参加への感謝」を伝え、一本締めや三本締めなどで場を整えます。締めの挨拶は、忘年会全体を気持ちよく終えるために重要な役割を果たします。
忘年会の挨拶で使える例文集
忘年会の挨拶は、長く話す必要はありません。1〜2分以内で簡潔にまとめ、感謝の言葉と来年への前向きな一言を添えることが基本です。以下に、シーンごとに使いやすい定番の例文をご紹介します。
開会の挨拶の例文
忘年会のスタートを告げる開会の挨拶は、役職が最も高い人が担当するのが一般的です。短く全体への感謝を伝えると、会の雰囲気が引き締まります。
|
皆さま、本日はお忙しい中、忘年会にご出席いただきありがとうございます。 それでは、どうぞ本日の会をお楽しみください。 |
乾杯の挨拶の例文
乾杯の挨拶は、会場全体を盛り上げる大切な役割です。明るくシンプルに言葉をまとめると、自然に乾杯へとつなげられます。
|
皆さま、本日は一年間の労をねぎらい、こうして集まることができ大変うれしく思います。来年も健康で実り多い一年となりますよう願いを込めて、乾杯いたしましょう。 それでは、ご唱和をお願いします。乾杯! |
開会と乾杯をまとめる場合の例文
人数や進行の都合によっては、開会と乾杯を一度にまとめるケースもあります。その場合も「感謝+一年の振り返り+乾杯」の流れを押さえましょう。
|
皆さま、本日はご多忙のところお集まりいただきありがとうございます。今年も一年、大変お世話になりました。ここで皆さまへの感謝の気持ちを込め、乾杯のご発声をさせていただきます。 今年も1年お疲れさまでした!!乾杯! |
締めの挨拶の例文
締めの挨拶は、会を気持ちよく終えるための重要な役割です。感謝と来年への抱負を添え、一本締めや三本締めでまとめると自然です。なお、一本締めか三本締めかは会社や地域の習慣によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
|
皆さま、本日は最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。 本年は多くのご支援とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。来年も引き続き、力を合わせて良い一年を築いていきましょう。 それでは一本締めで締めたいと思います。皆さま、ご唱和をお願いします。 |
忘年会を盛り上げる一言アイデア
定番のフォーマルな挨拶に加えて、場の雰囲気を和ませる一言を添えると、忘年会らしい明るさが出ます。ただし、笑いを狙う場合でも、人を傷つけたり立場をからかうような発言は避け、場が和む程度にとどめることが大切です。ここではシーン別に使いやすいアイデアをご紹介します。
なお、挨拶に一言添える場合は、盛り上げたい気持ちが逆効果になることもあります。
そのため、次の点に注意するようにしましょう。また、面白さやユーモアは笑わせるよりも和ませるを意識するようにしましょう。
- 性別・年齢・役職、立場など属性に触れる冗談は避ける
- 短くまとめる
- 声はハキハキと自信を持って伝える
遅刻者がいる場合のユーモアある開会宣言
参加者が全員集まっていない状況で会をスタートさせることもあるかと思います。そのような時は、そのアクシデントをユーモアある挨拶に変えて伝えると、場の雰囲気を和やかにすることができます。
先に紹介した例文に、リアルタイムな状況を加えることでより柔軟な開会宣言となります。
|
皆さま、本日はお忙しい中、忘年会にご出席いただきありがとうございます。 【ここに一文追加して伝えてみましょう】 本年も皆さまのお力添えにより、無事に一年を終えることができました。心より感謝申し上げます。 |
加える一言は、遅れてくる人に配慮した内容が望ましいでしょう。
【一言例文】
|
まだ全員はそろっていませんが、私の喉がカラカラなので先に始めさせていただきましょう。 |
|
どうやらまだ仕事が納まっていない方もいらっしゃるようですが、時間になりましたので開始させていただきます。 |
|
遅れてくる方は二次会で活躍していただくとして、先に乾杯の準備を進めたいと思います! |
乾杯の挨拶にユーモアを添える場合
乾杯の挨拶は、会場全体を一気に盛り上げる大切な役割です。フォーマルな言葉をベースに、軽い一言を差し込むことで、より雰囲気が和やかになります。
先に紹介した例文に、一言ユーモアを加えてみましょう。
|
皆さま、本日は一年間の労をねぎらい、こうして集まることができ大変うれしく思います。 【ここに一文追加して伝えてみましょう】 来年も健康で実り多い一年となりますよう願いを込めて、乾杯いたしましょう。 |
加える一言は、場を和ませる内容が望ましいです。仕事や個人を直接いじるのではなく、「全体の出来事」や「自分の感想」をネタにすると安心です。
【一言例文】
|
私が今年一番大変だったのは、忘年会の日程調整です!ぜひ、私を労ってください(笑) |
|
今年一番の大きな声で乾杯をして、疲れを一気に吹き飛ばしましょう! |
|
アルコールでもソフトドリンクでも、好きなものではじけましょう。皆さんご一緒に、乾杯! |
締めの挨拶にユーモアを添える場合
締めの挨拶は、忘年会を気持ちよく終えるための重要な役割です。基本は感謝と来年への抱負を伝え、一本締めや三本締めでまとめます。ここに軽いユーモアを添えると、最後まで明るい雰囲気で会を終えられます。
先に紹介した例文に、一言ユーモアを加えてみましょう。
|
皆さま、本日は最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。本年は多くのご支援とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。来年も引き続き、力を合わせて良い一年を築いていきましょう。 【ここに一文追加して伝えてみましょう】 それでは一本締めで締めたいと思います。皆さま、ご唱和をお願いします。 |
加える一言は、二次会や飲み過ぎ注意など、全員が共感できる軽い話題が無難です。場の雰囲気が真面目なときは、無理にユーモアを入れず、フォーマルのままでも十分です。
【一言例文】
|
これで締めますが、二次会、三次会とまだまだ、今年は終わらせませんよ!! |
|
これで締めますが、財布のひもはまだ締めないでくださいね! |
|
来年も健康第一で頑張っていただきたいので、二次会では飲みすぎないようにしてくださいね! |
挨拶をお願いする時に幹事さんが注意しておくポイント
幹事にとって、忘年会の挨拶を「誰にお願いするか」は重要な準備のひとつです。依頼の仕方を間違えると相手に負担をかけたり、場の空気を乱してしまうこともあります。ここでは幹事が押さえておきたい注意点をご紹介します。
依頼は臨機応変に対応できるようにする
挨拶をお願いする人は、基本的には役職順に決めておくのが安心です。ただし、当日の参加者の顔ぶれや急な欠席などによって柔軟に対応する必要があります。事前に複数の人に同時にお願いすると角が立つこともあるため、普段から候補をイメージしておくにとどめましょう。当日に欠席が分かった場合は、その段階で上司に相談し、代わりの方に依頼するのがスマートです。
同格が複数いる場合は上司に相談
役職が同じ人が複数出席する場合、幹事が独断で決めてしまうと『なぜ自分ではないのか』と誤解を招きかねません。事前に確認しておくことで、依頼を受ける側も安心して準備ができます。その際は直属の上司や役員に相談し、誰にお願いするのが適切かを判断してもらうようにしましょう。
接待色が強い場合は自社でまかなう
取引先との忘年会など、接待要素が強い場合は自社のメンバーが挨拶を担当するのが基本です。取引先にお願いすると『自分たちで進行できないのか』という印象を与えることもあります。幹事が責任を持って自社内で完結させることが信頼につながり、相手に負担をかけずに会を進めることができます。そのため、幹事側で事前に段取りを整えておくことが大切です。
まとめ
忘年会の挨拶は、開会・乾杯・締めなどそれぞれの場面で役割があり、基本的には役職や立場に応じて担当する人が決まります。フォーマルな例文をベースにすれば失敗がなく、さらに一言ユーモアを添えることで場の雰囲気を和ませることもできます。
一方で、ユーモアを狙いすぎると逆効果になることもあるため、「人を傷つけない」「短くまとめる」「自信を持って伝える」ことを意識することが大切です。
また、幹事は挨拶をお願いする相手を事前に把握し、当日の欠席や状況の変化にも対応できるよう準備しておきましょう。特に取引先との忘年会では、自社側で挨拶を担当するなど、相手に配慮した段取りも欠かせません。
忘年会は、一年の労をねぎらい、来年への前向きな気持ちを共有する大切な場です。基本を押さえつつ、自分たちらしい言葉で挨拶をすることで、参加者全員が心地よく締めくくれる会になるでしょう。