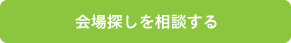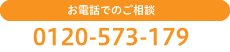忘年会や新年会で使える余興・出し物の種類や選び方のポイントを解説
2020/1/7
2023/11/22
忘年会や新年会の出し物や余興で、何をすれば良いか迷っていませんか?出し物や余興を何にするか決める前に、選び方のポイントを知っておきましょう。今回の記事では、忘年会や新年会で使える出し物や余興の種類、選び方のポイントについて解説しています。
これから余興や出し物を決める方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
【定番・盛り上がる】余興や出し物の例

画像素材:PIXTA
忘年会で盛り上がる、定番の余興や出し物の例をチェックしていきましょう。
|
モノマネ・一発芸
余興や出し物の定番のひとつとして、モノマネや一発芸があります。その年に流行っている芸人さんや、テレビで話題のモノマネは、年齢や性別に問わず知っている可能性が高く、盛り上がるでしょう。
また、会社の忘年会や新年会であれば、上司や同期のモノマネもおすすめです。その会に参加している人にしか分からない、共通の笑いが誘えるかもしれません。
テレビで話題となっている人や地名度が高い人のモノマネをする場合は、他の参加者と同じ内容の出し物となる可能性があるため、幹事への確認が必要です。
ヒゲダンス
余興や出し物でよく行われるのがヒゲダンスです。音楽に合わせ、投げたマシュマロを口でキャッチするなどのちょっとしたコンビ芸を取り入れ、成功すると盛り上がりが増すでしょう。
失敗をしても、音楽があるため、演技でごまかすこともでき、見ている参加者を芸の中に誘い、突然挑戦させるなどの面白さもあります。ヒゲダンスを知らない人でも、その場で芸を見て理解できる内容なので、参加者全員が楽しめるでしょう。
二人羽織
2人1組になり、縦に重なります。上から羽織を被り、後ろの人は顔が隠れ手だけ前に出ている状態にしましょう。前の人は羽織から顔のみが出ている状態を作ります。
前の人の指示に合わせ、後ろの人が手を動かし、前の人が上手に食べることができるかどうかを披露するものです。指示を無視し、自由に手を動かすことも面白く、盛り上がるでしょう。
チーム戦でどちらが綺麗に食べることができるか、参加者に判定してもらうのも楽しみ方の1つです。場合によっては、床や服が汚れてしまうかもしれないため、会場や周りの状況を確認した上で行うようにしましょう。
漫才
オリジナルの漫才は、忘年会で人気の出し物の1つです。3~5分程度にまとめ、1年で起きたことを盛り込みながら作成しましょう。会社や部内の出来事、上司のモノマネなどを取り入れると盛り上がります。
漫才を披露する場合は、事前に練習して、はきはきと喋るようにしましょう。会場が広い場合は、マイクが使用できるか事前に確認しておくと良いです。
【事前準備・練習なし】余興や出し物の例

画像素材:PIXTA
忘年会までに練習や準備をする時間があまりない、という方におすすめの余興や出し物の例をチェックしていきましょう。
|
イントロクイズ
急に余興や出し物を頼まれた際に、携帯1つで行うことができ、会を一気に盛り上げることができるものが、音楽を使ったイントロドンゲームです。誰もが知っていそう、もしくは話題の楽曲のイントロを2〜3秒流し、参加者になんの曲だったのかを答えてもらいましょう。
イントロゲームを毎回やっていて他の楽しみ方がしたい、という方にはアウトロゲームがおすすめです。曲の最後何秒間かを流して、曲名を当ててもらいます。イントロクイズより難しいため、音楽好きな人の集まりでの余興にぴったりです。
ジェスチャーゲーム
お題を決め、出されたお題に合わせてジェスチャーをする人と回答者に分かれ、ゲームを行います。とくに用意するものはなく、参加者が一生懸命身体を使ってお題を伝えようとする姿は面白さがあり、盛り上がるでしょう。
お題を「スポーツ」「動物」などの簡単なものにすると当たりやすくなりますが、「このスポーツをしているのは誰でしょう」「何をしている動物でしょう」のように、お題を難しくして出すことで、ジェスチャーをする人の必死さが増し、ゲームが一層盛り上がります。
ロシアンルーレット
たこ焼きやシュークリームをいくつか用意し、1つだけデスソースやワサビを入れておきましょう。何人かで食べて、誰が辛いものを選んだか当てるゲームをすると盛り上がります。ロシアンルーレット用の食べ物を用意する必要がありますが、お店によってはメニューにある場合があるので、事前に確認してみると良いでしょう。
【誰でも参加しやすい】余興や出し物の例

画像素材:PIXTA
忘年会に参加している誰もが参加しやすい余興や出し物の例をチェックしていきましょう。
|
ロープ・手押し相撲
すぐにできる出し物の中には、対戦者が向かい合い、合図に合わせて手を押したり引いたりする手押し相撲があります。定番の手押し相撲ではなく、短いロープを2本使い、手押し相撲と同じルールでゲームをする方法もあります。
さらに難しくしたい場合には、片足立ちにし、バランス感覚で勝負してみましょう。片足立ちにする場合は、転んで怪我をしないためにも、座布団やタオルで、クッションを作るといった工夫をしておきましょう。
ビンゴ
ビンゴは定番だからこそ誰でも簡単に参加することができますが、列を揃えるのに時間がかかり、飽きてしまう可能性があります。その場合は、数字ではなくオリジナルのビンゴを作成してみましょう。
たとえば、芸能人の写真をクジにし、ビンゴカードには芸能人の名前を書くことや、社員の幼少期の写真をクジにし、どの社員の写真なのかを当てていく、などの一工夫をすることで、クイズが混ざったビンゴゲームが楽しめます。
クイズ大会
会社や友達同士の忘年会や新年会であれば、参加している方達にしかわからない内容をクイズ形式で出題し、正解数を競います。正解数が多い人に景品を用意しておくと、参加者が積極的に楽しんでくれるでしょう。
「企業理念の〇〇に入る言葉は何?」はもちろんのこと、「この人にしかわからないだろう」という問題をサービス問題として出題すると面白さにつながる場合があります。問題を工夫することで盛り上がり方も変わるため、出題者の腕の見せ所となります。
【参加者同士の仲を深める】余興や出し物の例

画像素材:PIXTA
普段あまり関わりがない部署の人や新入社員が参加している忘年会で使える、中を深めやすい余興や出し物の例をチェックしていきましょう。
|
連結輪くぐり
ロープや紙リボンで、身体が通る大きさの輪を作ります。3〜5人のチームを作り、各チーム手を繋ぎ端の人に輪をかけます。手を離さずに、先に最後の人まで輪を繋げられたチームの勝ちとなります。
手を離さなければ、寝ることや抱きつくこともOKとなるため、女性チームと男性チームに分かれてゲームを行うといいでしょう。輪を繋げるには、身体を色々と動かすことやチームの協力も必要となるため、社員同士、友達同士の仲も深まります。
アイドルダンス
練習時間を設け、チームワークを生かして有名アイドルのダンスを完コピで披露します。最初は思うようにできなくても、練習を重ねることで徐々にレベルアップし、チームの団結力が深まります。
団体芸となるため、練習時間の確保は必要となりますが、楽曲に合わせた衣装を身に付け、恥ずかしがらずに全力でアイドルになりきることで、盛り上がるでしょう。
伝言ゲーム
伝言方法は様々で、背中に指で文字を描いて伝言していく方法や、口パクで伝言するなどがあります。人数が多ければ多いほど、上手く伝わりにくく、面白い回答に結びつくため、5人以上で行うといいでしょう。
チーム戦となるため、チームの協力が必要となり、普段接点のない人同士でチームを組むことにより、コミュニケーションを取るきっかけになります。
【笑いあり感動あり】余興や出し物の例

画像素材:PIXTA
感動する出し物をしたい、という方におすすめの余興をチェックしていきましょう。
|
ダンス・歌・演奏
ダンスや歌、楽器の演奏など、特技を活かした出し物は見ている人に感動を与えられるでしょう。また、意外な特技を披露することで、普段あまり接点がない人と会話をするきっかけにもなります。
感動を与えたい場合には、どのような曲を披露するかも重要です。つい聞き入ってしまう雰囲気を作れるよう、楽曲にはこだわりましょう。
ムービー・スライドショー
今までの思い出や今後の目標をスライドショーやムービーにして流し、笑いと感動を与えましょう。忘年会であれば1年間を振り返ることができ、新年会であれば1人1人の紹介に加え、新年の目標を発表する場にできます。
仕事中の何気ない写真やイベント時に撮った写真など、あまり見返すことがない写真でも、みんなで見ることで、懐かしさもあり、中には感動する人もいます。仲の良い友達同士であれば、出会った頃の写真を入れると、より盛り上がる場合があります。
忘年会・新年会の余興や出し物を選ぶための5つのポイント

画像素材:PIXTA
忘年会や新年会は、会社や友達同士、近隣の集まりなど様々な場所で開催されます。どの場面で行う忘年会や新年会であっても、盛り上がる余興や出し物をするためのポイントを知っておきましょう。
|
参加者全員が楽しめる内容を選ぶ
会社や地域の忘年会、新年会では、幅広い年齢の方が参加するでしょう。参加者全員が楽しめるように、誰もが知っている内容の出し物や余興を選びましょう。
年齢に関係なく楽しめる内容であることはもちろん、特定の人にしか分からないものや、特定の趣味がある人にしか分からないものは避けた方が良いです。
他の人と同じ内容を避ける
複数の余興や出し物を行う場合、他の人と同じ内容にならないように注意しましょう。同じような内容の出し物や余興が連続すると、見ている人が退屈してしまう可能性があります。
出し物や余興を担当する場合は、他の人がどのような内容を選んでいるか確認し合いながら準備をすすめましょう。
同じ内容で準備をしている場合は、1つにまとめて披露できるか幹事に確認して調整すると良いです。特に、流行っている曲やダンスは重複してしまう可能性が高いので注意しましょう。
会場に合った出し物を行う
会場が貸し切り、または他のお客さんがいない状態であれば、自由に考えることができます。しかし、居酒屋やレストランの一画で他のお客様が見える会場の場合、周囲に迷惑がかからないような出し物を考えましょう。
大人数で盛り上がる出し物や余興は、他のお客様からクレームが入る可能性があります。忘年会や新年会で余興や出し物を行う場合は、できるだけ個室や貸し切りの会場を選ぶと良いです。
時間が長くなる出し物を避ける
忘年会や新年会を行う会場やお店によっては、滞在可能時間が決まっているケースがあります。会場やお店の滞在可能時間を超えないように、長くなる出し物や余興は避けましょう。忘年会や新年会は、全体を通して約2〜3時間程度で行われる傾向があります。
どのタイミングで出し物を行うかは様々ですが、参加者全員が参加する余興や出し物の時間は30分程度が理想です。
また、全員が参加をしない場合であっても、出し物の時間が長ければ長いほど見ていて飽きてしまう可能性もあります。他の披露者のことや、見ている人のことを考え、出し物を選びましょう。
下品な内容を避ける
忘年会や新年会が仲の良い友達同士の場であれば、下ネタや暴露ネタを披露しても楽しめるかもしれませんが、会社や近隣の組合での忘年会や新年会では、下品なネタほど不快だと感じてしまう人がいることを想定して避けましょう。
また、披露している人や一部の人のみが楽しんでいるという状況を作らないように意識しましょう。
忘年会の出し物を盛り上げるための注意点

画像素材:PIXTA
忘年会の出し物を盛り上げるための注意点を知っておきましょう。
|
効果音やBGMを使う
効果音やBGMを効果的に使うことで、出し物が盛り上がるでしょう。たとえば、クイズの回答時に「ピンポーン!」という効果音をつけたり、マジックの最中にBGMをつけたりすると良いです。音やBGMは参加者の意識を引きつけることもできるため、出し物に合わせたBGMを用意しておきましょう。
会場が居酒屋や他のお客様が見える場所では、BGMや効果音が使用できないケースが多いため注意が必要です。また、利用する会場に音響機器のレンタルが可能かどうか、事前に確認しておきましょう。
団体での出し物はしっかり練習する
ダンスや歌など、団体で行う出し物はしっかりと練習をしておきましょう。練習不足で出し物を披露すると、自信がないパフォーマンスになってしまい、見ている人が楽しめない可能性があります。
団体で行う出し物を行う場合は、練習時間が確保できるかどうかを事前に確認しておきましょう。完成度が高い団体での出し物は、見ている人の感動を誘います。
恥ずかしがらずに披露する
出し物は、恥ずかしがらずに胸を張って堂々と披露することで、自然と盛り上がります。恥ずかしがり中途半端に披露してしまうと、見ている人に内容が伝わらずに盛り上がらない可能性があるので注意しましょう。
あらかじめ練習をしたり、台本を用意したりすることで、緊張していても安心して披露できます。出し物の内容に関係なく、堂々と披露するように心がけましょう。
まとめ
忘年会や新年会では、参加している人全員が楽しめる内容の余興や出し物を選びましょう。団体で披露する出し物の場合は、しっかりと練習をして恥ずかしがらずに行うことが大切です。
急遽出し物や余興を頼まれた場合は、事前準備が必要ないイントロクイズやジェスチャーゲームなどがおすすめです。また、ダンスや歌など大きな音が出る余興は、貸し切りができる会場で行いましょう。